|
祇園祭 後祭 1
|

4年前に49年ぶりに復活された祇園祭の後祭です。
前祭より圧倒的にに見物客が少なく、巡行時間の40分前に
行けば、辻回し(河原町御池)の最前列で山鉾がきしむ音と
引き手の熱気が伝わって来る見物が出来る。写真は大船鉾
|
|
祇園祭 後祭 2
|

その昔、祇園祭のメインイベントは17日の山鉾巡行と24
日の還車でした。前祭は絢爛豪華で大勢の人が集まる山鉾巡行に対して後祭の還車は神様が神輿で厳かに神社に
帰って行かれる事から、見物に行っても時期遅れで何もない
後の祭り・・・の語源と言われているらしい。写真は北観音山
|
|
祇園祭 後祭 3
|

今は10基の山鉾巡行で、前祭とくらべても、人の少なさで
私(老人)には後の祭りがオススメ。
辻回しに使う竹と音頭取り、引き手、水撒きが一体となって
10トンの鉾が向きをかえる。
|
|
祇園祭 後祭 4
|

山中越えの桜を見上げている大伴黒主(歌人)山中越えは
平安時代には多くの歌に詠まれ、桜の名所であったらしい。
写真は黒主山
|
|
大溝城跡 1
|

JR高島駅より南に300m、少し分かりにくいが高島病院
南隣に大溝城跡がある。1578年 信長が織田信澄に築城
させた。設計は明智光秀と伝わっている。
|
|
大溝城跡 2
|

信長が築いた琵琶湖水城、四城(安土、長浜、坂本)の
一つである。乙女ヶ池を外堀に琵琶湖に通じていた。
|
|
大溝城跡 3
|
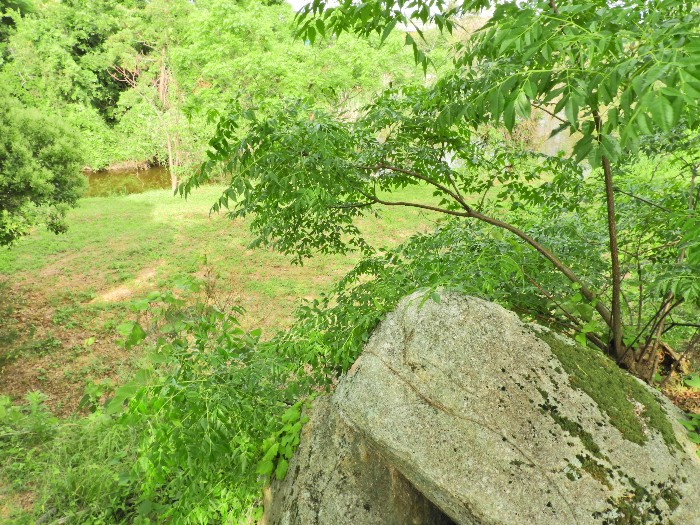
3年前にに発掘調査現地説明会に行ったが、確かこの辺りに
天守に横付けの船乗り場が発掘されていた(石垣のしたから
水路方向)現在は埋め戻されている。
|
|
大溝城跡 4
|

浅井三姉妹の(茶々、お初、お江)一人、お初が京極高次の
正妻として新婚時代の三年間をこの城ですごした。
|
|
川端 1
|

高島市新旭針江に行ってきました。170戸あまりの小さな
集落には、110戸が生水(しょうず)と呼ばれる湧き水を
家庭内に10m〜20mの鉄管を打ち込み自噴する清らかな
水を飲料水や炊事に使っています。これを川端(かばた)と
呼んでいます。
|
|
川端 2
|

針江の真ん中を流れる針江大川では毎年、夏に入ると
この地域の子供が・・・ハッポースチロール板で遊んでいる
|
|
川端 3
|

流れの綺麗な針江大川には涼しそうに梅花藻が揺れています
|
|
川端 4
|

比良の伏流水、生水を日本酒造りに、私は呑めないので
|
|
川端 5
|

正傳寺境内にある湧き水をコーヒー用に持って帰りました。
|
山中比叡平「歴史散歩」 【補遺】②
![[Image]](yamagara.gif)